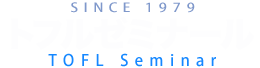「英語を学ぶと同時に、現代人として生きる上での教養を身につけることができる単語集」というコンセプトのもとに制作された『「知」への英単語』ですが、刊行以降たくさんの反響をお寄せいただきました。中でも多かったコメントは、学びを深めるために付した読書案内が12冊では物足りない、もっと勉強したいというものでした。そこでこのサイトでは、『「知」へのブックガイド』と題して、さらに教養を高めるための本を経済、政治哲学、社会、外交・安全保障、歴史、自然科学の6つのジャンルから、30回の連載で紹介することにいたしました。いずれも、さまざまな議論の際に役立つ国際標準の教養が身につくものです。皆さまの学習のご参考にしていただければ幸いです。
――星 飛雄馬
1928年、日本を含む世界63ヵ国がケロッグ=ブリアン条約を批准したことによって、戦争を違法とする流れが定まった。それまで戦争は合法なものと考えられてきた国際法の世界において、これは真に画期的なことであった。
こうした「戦争の違法化」という思想のルーツの一つと考えられているのが、今回紹介するカントの『永遠平和のために』である。ケロッグ=ブリアン条約が成立したのが20世紀であることを考えると、18世紀を生きた哲学者のカントが戦争の違法化という構想を思いついていたということは、極めて先見性のあることだと言えるだろう。
永遠平和を実現するために、カントは6つの予備条項と、3つの確定条項からなる9つの条件を満たすことが必要であると説く。予備条項の中で重要なのは、まず「独立して存続している国は、その大小を問わず、継承、交換、売却、贈与などの方法で、他の国家の所有とされてはならない」という第2条項である。カントの生きていた時代、彼の母国であるプロイセンの隣国ポーランドは、国際情勢の中で三度にわたりロシアなどの国々に分割されるという悲劇があった。カントは、私たちが他人の人格を単なる手段のように扱うことを戒め、常に目的そのものとして扱わなければならないと説いた。それと同様に、国というものも、ただの物件のように譲渡したり、交換したりしてはいけないのだと考えたのである。
第2条項以外に予備条項の中で重要なのは、「常備軍は、いずれは全廃すべきである」とする第3条項であろう。カントは、常備軍の存在は他国にとって脅威となり、それはやがて際限のない軍拡競争へと行き着くと考えていた。「いずれは」と条項にあるように、カントもそれがすぐに実現するとは考えていなかったようだが、その発想は20世紀になり、日本国憲法第9条において、「戦力の不保持」といった形で結実することになる。
続いて、確定条項を見ていこう。第一確定条項は、「どの国の市民的な体制も、共和的なものであること」とされている。古来より国家の形式には君主制、貴族性、民主制といったものがあるとされてきた。だが、カントはこうした区別はそれほど重要ではないと指摘する。直観的には民主制のほうが君主制や貴族性といった体制よりも、より好ましいように思われる。けれども、民主的であるからといって、独裁的、専制的な体制にならないとは限らない。20世紀のイタリアやドイツを見てみれば、民主的な体制からファシズムが生み出されていったことがよくわかる。
そこでカントが重視するのが、共和的であるか、専制的であるかという区分である。カントは共和的な体制のほうが専制的な体制に比べ、より平和的であるという。それはなぜだろうか?
専制的な体制では、独裁的なリーダーが独断で戦争をすることを決めることができる。それに対し共和的な体制では、「戦争をするかどうか」について、国民の同意を得る必要がある。戦争が始まれば国民は徴兵され、戦場で兵士として戦わなければならないかもしれない。また、戦争によって国家の財政が悪化すれば、国民は納税によってそのコストを支払わなければならない。よって共和的な体制の国家では、むやみに戦争を他国に対して仕掛けることはなくなる、というのがカントの考えだ。
このようにカントの平和論は理想主義的な空理空論ではなく、論理的かつ実現可能なものである。彼の思想は、今日の政治哲学や政治学の考えのベースにもなっている。18世紀に書かれた古典ながら、今日でも十分読む価値のある一冊と言えるだろう。

私たちが第二次世界大戦について考えるとき、思い浮かぶのはどんなイメージだろうか? 戦争から70年以上の時がたち、私たちの多くは実際に戦争を体験していない。そのため、戦争という言葉から連想するのは、あくまで映画やドラマといったメディアを通じて得たイメージとなる。それらの多くは、東京大空襲や広島、長崎への原爆投下といった、日本人が戦争によって直面した悲劇が中心となるであろう。
本書の著者である細谷雄一は、日本人の第二次世界大戦観は一面的なものであり、その歴史認識には偏りがあることを指摘する。確かに、東京大空襲は民間人に対する無差別虐殺であり、歴史の悲劇である。だが、私たちがその悲劇を心に刻み、深く受け止めるのであれば、それと同時に1931年に関東軍が行った錦州爆撃についても忘れてはならないと、細谷は主張する。
1931年10月、関東軍は満州鉄道沿線から離れた錦州に爆撃機を展開し、大規模な空爆を行った。その結果、多くの非戦闘員が無差別に殺害された。この爆撃は明らかに自衛の範囲を超えるものであり、1928年に締結されたケロッグ=ブリアン条約に違反するものと考えられる。だが、それにもかかわらず、関東軍はその後も上海、南京、重慶といった地で、非戦闘員に対する無差別爆撃を続けた。こうした国際法違反と考えられるような行為を、なぜ日本軍は行ってしまったのだろうか?
歴史を遡って見てみると、日本軍はそもそも国際法を軽視するような組織ではなかったことが分かる。1904年に始まった日露戦争において、日本は世界の国々の中でも、とりわけ国際法を遵守する国家であった。なかでも、ロシア人の戦争捕虜に対する取扱いは世界でも評判となり、日本の国際的地位の向上に寄与するものとなった。日本軍は、この戦争に先立って制定されたハーグ陸戦条約を守り、捕虜を人道的に取り扱った。そのため、捕虜収容所におけるロシア人捕虜の死亡率は0.5%と、当時の戦争捕虜の死亡率としては極めて低いものとなった。こうした日本軍の捕虜の取り扱いに対し、戦後ロシアから謝意が表せられるということまであったほどである。
このように当時の日本軍が国際法を遵守し、世界中の国々から尊敬される存在となることができたのは、軍部で徹底的な国際法教育を行っていたためである。当時の日本の軍隊のレベルは非常に高く、下士官兵ですらハーグ陸戦規則やジュネーヴ条約の主旨を理解していたという。明治時代の日本の軍隊のレベルの高さは、教育の賜物だったのである。
だが、そうした国際感覚に富んだ日本の軍部も、昭和に入ると変質してくる。1929年に世界各国がジュネーヴに集まって締結した「俘虜の待遇に関する条約」を、日本は批准しなかった。昭和の日本軍内では、捕虜になることは恥辱であるという認識が強かったためである。 1932年になると、陸軍士官学校の教程から戦時国際法の科目が除外された。さらに1937年以降は、国際法教育は基本的に中止されてしまった。昭和の日本軍は、国際法教育は不要なものであると判断したのである。
その結果として、多くの日本の将校、下士官が国際法を理解しないまま、戦地に赴くこととなった。それはやがて、敗戦後に捕虜の虐待などを理由として、BC級戦犯裁判で多くの日本軍人が処刑されるという悲劇を生み出す。こうした事態を招いた責任は、彼ら現地の軍人にではなく、国際法教育を十分に行わない方針を決めた軍の指導部にあったのではないかと細谷は語る。
国際法を学ぶこと、そして国際感覚を養うことがいかに大切かということを、深く感じさせてくれる一冊である。
憲法について議論となるとき、必ずといっていいほど話題の中心となる9条。そこで規定されている戦争の放棄は、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義の精神を表したものとされる。だが、こうした戦争の放棄という発想は、本当に日本国憲法に固有のものなのだろうか?
イェール大学法学部教授として活躍するオーナ・ハサウェイとスコット・シャピーロは本書において、いかにして人類の歴史の中で戦争を禁止するという発想が生まれてきたのか詳細に記述している。著者らによれば、その分岐点は第一次世界大戦後に日本を含む世界の先進国間で結ばれた、ケロッグ=ブリアン条約(パリ不戦条約)に遡るという。
そもそも、近代において戦争は合法なものであると考えられてきた。その思想的ルーツは、17世紀のオランダの法学者、フーゴー・グロティウスにある。当時のヨーロッパでは、おもに宗教的な対立から三十年戦争に代表される無秩序かつ大規模な殺戮が常態化していた。その状況においてグロティウスは、戦争の存在そのものは否定できないまでも、一定のルールの下に行われるべきことを唱えた。
だが、そのようなグロティウス的な考え方は、やがて行き詰まりをみせるようになる。毒ガス・戦車・飛行機・潜水艦などの新兵器が導入された第一次世界大戦の死傷者は、それまでの戦争とは桁外れの数にのぼった。そのことが、世界各国の指導者に戦争そのものを回避する道を模索させることとなったのだ。そして、その結果として生まれたのがケロッグ=ブリアン条約なのである。
ケロッグ=ブリアン条約によって、締結国が紛争の解決を戦争に訴えることは違法となった。この条約に参加した日本を含め、世界の国々は戦争を放棄したのである。このような歴史上の大転換を、著者らは「旧世界秩序」から「新世界秩序」への変化と呼んでいる。
日本においては、ペリーの来航に始まる開国によって国際法を学ぶ必要に迫られるようになった。国際法の専門家を養成するにあたって白羽の矢を立てられたのが、オランダ語に通じた西周(にし・あまね)であった。西はオランダに渡り、ライデン大学のシモン・フィッセリングの指導を受けることになる。フィッセリングはグロティウスの専門家でもあったため、西は旧世界秩序の国際法観を習得したことになる。
西によって日本の指導層の間に「戦争は一定のルールの下に行われなければならない」という考えが浸透した。そしてその常識の中で日清、日露と戦争を勝ち抜き、世界の中で影響力を高めていった。そんな日本にとって、大きな運命の分かれ道となったのが、1933年(昭和8年)の国際連盟からの脱退である。日本軍に対して満州からの撤退を勧告した国際連盟に対し、これを不服とした日本は連盟からの脱退を決意する。
この時点で、日本の指導層を含めた国民の多くは、世界の潮目が旧世界秩序から新世界秩序へと変化してしまっていることを理解していなかった。ケロッグ=ブリアン条約には加盟していたものの、それはあくまで建前であり、戦争が違法化される流れにあることの重大性を認識していなかったのである。
本書を読むと、生き馬の目を抜くような国際社会でサバイバルするためには、国際法の理解が欠かせないことがよくわかる。明治時代、不平等条約の改正が喫緊の課題だったため、国の指導層の多くは国際法をよく理解していた。それが昭和になり日本も先進国の仲間入りをすると、国際的な潮流に対して鈍くなってしまったのは、何とも皮肉なことである。真の国際人となるためには、国際法への正しい理解が欠かせないことは間違いのないことだろう。
2020年5月、コロナ禍の日本に更なる悲しいニュースが駆け巡った。女子プロレスラーの木村花さんが、ネット上の誹謗中傷が原因で自ら命を絶ったというのだ。ネット上の誹謗中傷が原因で亡くなる人は、木村さん以外にも有名人、一般人を問わずたくさんいる。また、ネットのSNSを覗いてみれば、政治的に極端な意見を主張する人々が毎日のように争っている。本書の著者である山口真一が2000人を対象にアンケートをとったところ、75%の人は「ネットには攻撃的な人が多い」と考えており、70%の人は「ネットは怖いところだ」と考えていることが分かったという。ネット上の言論の激しさを考えると、納得の数字だ。
海外の研究においても、ネット上には極端な意見の持ち主が多いということが示唆されている。南カリフォルニア大学准教授のパブロ・バルベラが、2012年に5万人のtwitter利用者の発言を分析したところ、極左と極右の利用者の発言頻度が極めて高く、また彼らの発言が全体に与える影響力が非常に高かったということが分かった。 なぜネット上では私たちの日常生活と異なり、人を傷つけるような極端な言論が幅を利かせるのだろうか。山口は最新の統計学や科学を利用しながらそのメカニズムを解き明かし、ネット言論の根源的な特徴を四項目に分けて分析している。①「極端な人」はとにかく発信する、②ネット自身が「極端な人」を生み出す、③非対面だと攻撃してしまう、④攻撃的で極端な意見ほど拡散されるという四つが、山口が見出したネット言論の本質である。
ネット上では、私たちの日常生活と異なり、極端で声の大きい人が、誰にも止められることなく、大量に発言することが可能だ。中庸でおとなしい人は、ネット上ではほとんど発言をすることがない。ネット上で発言するのは「発信したい人」だけである。言い換えるなら、ネット上の言論空間とは、「能動的な発信」だけで形作られたものであると言える。こうしたタイプの言論空間に私たちが触れるのは、有史以来、初めてのことであると山口は指摘する。
そのことを示す分かりやすい調査を、山口は本書の中で紹介している。山口は20代~60代の男女3000名を対象に憲法改正に関するアンケート調査を行った。憲法改正について、「非常に賛成である」から「絶対に反対である」まで7段階の選択肢を用意し、意識調査をおこなったのである。そしてさらに、その話題についてSNSに書き込んだ回数についても、同様な調査を山口はおこなっている。
すると、驚くべきことが分かった。なんと、最も人数が少なかったはずの両極端な「非常に賛成である」と「絶対に反対である」という選択肢が、ネット上での投稿された総回数では1位、2位となったのである。より詳細に数字を挙げると、「非常に賛成である」「絶対に反対である」という人は社会には7%ずつしかいないのに対し、ネット上では29%と17%という結果になった。実際には「賛成とも反対ともいえない」という中庸な選択肢を選んだ人が30%以上と圧倒的な多数派だったにもかかわらず、ネット上では極端な意見が強い存在感を示すことになったのである。
ここから分かることは、ネット上の言説は極端に走りやすく、実態を正確に反映していないということである。ネットとは、同じ考えや主義を持つ人々が繋がりやすい空間である。また、閉じたコミュニティの中で同じような意見に囲まれ続けると、意見が過激化する傾向もある。私たちはこうしたネットの特性をよく理解し、ネット上の意見にみだりに惑わされないようにする必要があるのではないだろうか。
私たちの身の回りには、健康をテーマにした番組やCMが溢れている。また、ネットの普及により、そうした健康情報の量そのものも、ネットが登場する以前に比べ、飛躍的に増大している。氾濫する健康情報の中には間違ったものも含まれているが、情報の洪水の中で、何が正しい情報なのか知ることは、私たちにとって困難である。
健康法について書かれた本でよくあるパターンは、個人の経験に基づいた話である。このような健康法を実践したら健康になった、病気が治ったといった類の話だ。だが、そういった体験談は嘘ではないかもしれないが、他人に適用された場合に再現性があるかどうかは分からない。私たちが何らかの健康法を実践する際には、その方法が客観的なエビデンスに基づくものであるかどうかを確かめることが大事だろう。
ここで言うエビデンスとは科学的根拠のことである。エビデンスにはレベルがあり、強いものから弱いものまで、さまざまな段階が存在する。それらのエビデンスを得るための医学研究には、大きく分けて「ランダム化比較試験」と「観察研究」という2種類のものがある。
ランダム化比較試験では、まず、研究対象となる人を、くじ引きのような方法によって、全く同じになるように2つのグループに分ける。そのあとに、片方のグループだけに健康に良いと思われる食品を摂取させ、もう片方のグループには接種させない。そうすることによって、2つのグループはその食品を摂取しているかどうか以外の条件がほぼ同じとなり、その食品が健康に及ぼす効果について、厳密に測定することが可能となる。
一方、観察研究ではある特定の食品をたくさん摂取しているグループと、あまり摂取していないグループを選び、それらを比較することによってデータを収集する。観察は年単位でおこない、場合によっては数十年データを収集し続けることもある。そうしてデータを集めた上で、2つのグループについて、病気になっていたり死亡していたりする割合を分析する。こうした観察研究にも十分意義はあるが、特定の食品をたくさん摂取している人々が、あまり摂取していない人々に比べ何か別の特徴を持っている可能性があるため(例えば、野菜をよく食べる人々は、運動もよくする傾向にあるなど)、純粋に食品の影響を抽出することが困難なことから、ランダム化比較試験に比べてエビデンスが弱いと考えられている。
こうした厳密なテストをクリアーした、科学的根拠にもとづいた正しい食事とはどのようなものなのだろうか。本書によれば、それは①魚、②野菜や果物(じゃがいもは除く)、③玄米や全粒粉などの炭水化物、④オリーブオイル、⑤ナッツ類といった5つの種類の食物をとることであるという。 反対に、健康に悪い食事についても、既にエビデンスが確立している。具体的には、①牛肉や豚肉といった肉類(鶏肉は除く)、②精製された米や小麦粉などの炭水化物、③バターなどの飽和脂肪酸といった3つの種類の食品が身体によくない食べ物だ。
このように本書には、どのような食事をとれば、がんや脳卒中などの病気になりにくくなり、長生きできるのかが具体的に書いてある。それらは皆、個人的な体験談などではなく、科学的なエビデンスに基づいたものであり信頼性が高い。健康に良い食事、悪い食事の項目はシンプルだが、実際に食事をする際に注意すべき点に数多く触れている。科学的根拠に基づいた身体によい食事に関心を持った方は、ぜひ本書の内容をよく読んでメニューを選ぶ際の参考にしてほしい。
現代の政治哲学には、さまざまな立場がある。中でも代表的なものには、リベラリズム、リバタリアニズム、コミュニタリアニズムなどがあるが、本書で紹介されている立場はリバタリアン・パターナリズムという聞きなれないものだ。
リバタリアニズムは日本語で「自由至上主義」とも訳される立場で、政府などの統治権力からの介入を極力拒否するような思想を意味する。一方、パターナリズムは父権主義とも訳され、権威者が相対的に弱い立場のものに積極的に介入する思想を指す。著者らによれば、リバタリアン・パターナリズムはそれら二つの立場の折衷案のようだが、果たして水と油のような二つの立場が両立するものなのだろうか?
著者らによれば、リバタリアン・パターナリズムでは、純粋なパターナリズムのように人々に行為の選択を押し付けることはしない。また、選択肢を制限することもしない。だが、それと同時に、人々が自己決定をする能力を最大限に尊重して、自由放任的に何でも自分で決めることを勧めるわけでもないという。 そのようなリバタリアン・パターナリストが思い描く社会で重要な役割を果たすのが、「選択アーキテクト(設計者)」である。選択アーキテクトとは人々が意思決定する際に、それがより有意義な選択となるようサポートする役割の人々のことだ。
選択アーキテクトが活躍する世界を具体的にイメージするために、著者らが出している例に肥満の問題がある。アメリカの肥満率は、いまや20%に達するほどで、アメリカ国民の六割以上が肥満か太り過ぎだと考えられているという。日本や中国の肥満率が5%未満であることを考えると、これは驚くべき数字だ。肥満の問題に悩まされているのはアメリカだけではない。世界保健機関(WHO)によると、アメリカ以外でもイギリス、東ヨーロッパ、オーストラリアなどの地域で1980年以降、肥満率が三倍になっているという。肥満は心臓病や糖尿病のリスクを高め、私たちの寿命を縮めることを考えると、問題の深刻さがよくわかる。
ここまで肥満が増えているということは、私たちが普段の生活でそれほど理性的に振る舞うことはできないということを意味するだろう。どのような食事を、どの程度とるのが正しいのかといった知識は科学的に確立している。にもかかわらずそれを実践できないのは、私たちにそうした正しい知識がないか、知識があっても欲望に負けて適切な食生活を実践できていないからだろう。
そこで登場するのが選択アーキテクトである。選択アーキテクトは、私たちがより理性的な判断ができるよう、さまざまな場面でサポートをする。大学のカフェテリアを選択アーキテクトがプロデュースする場面を想像してみよう。現在では、玄米のほうが白米より身体にいいことは、科学的に分かっている。そこで選択アーキテクトは、カフェテリアのメニューに玄米と白米の双方が選択可能であること、玄米のほうが健康的で、肥満を防ぐことを分かりやすく表記する。そして、場合によっては玄米のおにぎりをより目立つところに陳列したり、玄米のメニューを割引価格で販売したりと、私たちがより理性的な判断を下せるよう、ゆるやかに誘導していく。
こうした誘導のテクニックを、著者らはナッジ(Nudge)と呼んでいる。注意しなければならないのは、ナッジによる誘導は強制ではなく、選択の幅をせばめるものでもない、ということだ。カフェテリアでどんなナッジが使われていたとしても、私たちは白米のほうを選択する権利があるわけである。このように、まだまだ馴染みの薄いリバタリアン・パターナリズムだが、要注目の思想として、今後もより一層関心が高まっていくのではないだろうか。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の拡大が続き、私たちはライフスタイルの大きな転換を余儀なくされている。そのような中で、そもそも私たち人類とは何者なのか、という根本的な問いに対する関心も高まってきているように思われる。
本書の著者である市橋伯一は、人工的にRNAを作り出し、そのRNAに進化する能力を与えることに成功したという驚異的な実績を持つ研究者だ。「人類とは何者なのか」という問いに迫る探究者としては、まさにうってつけの人物と言えるだろう。
進化するRNAを生み出すところまでは成功した市橋だったが、その進化の「質」はあまり芳しいものではなかったという。何世代もの変化を経て、進化を見守ったものの、実験用のRNAが私たち人類のような複雑さを持った生命へと進化することはなかった。だが、この実験の結果こそが、私たち人類の正体へと迫る鍵なのではないかと、市橋は指摘する。
その謎を探るにあたって、まずは生命の進化をおさらいしてみよう。生命の中で最も単純なものは、細菌である。細菌は私たちの身体に欠かせないもので、納豆菌や乳酸菌などのように有用なものや、食中毒や病気の原因となる黄色ブドウ球菌や結核菌といったものが存在する。細菌は、地球上の生物の中で、最も種類と数の多い生き物だと言えるだろう。
地球上の生命として、最も初期の段階に生まれた細菌だが、時の流れと共にやがて進化の時を迎えることとなる。細胞膜という自らの殻を破り、他の細菌を細胞内に取り込むことによって、真核生物へと進化したのだ。取り込んだ細胞と取り込まれた細胞が、互いを排除することなく協力する関係を結んだことが、この進化の鍵である。
次の進化のステップも、同じような経路をたどることとなる。真核細胞同士が他を排除することなく、互いに協力することにより、多細胞生物へと進化に成功したのだ。多細胞生物となると、体もぐっと大きくなる。そして、細胞ごとに専門化することによって、眼や脳といった器官を手にすることも可能となった。
多細胞生物の中でも、アリなど一部の生物は個体間で協力し、一族全体として繁栄していく力を手に入れた。血縁個体間で協力することによって、社会性を身につけたのである。これもまた、協力を通じた進化と言える。そして私たちヒトは、アリやチンパンジーといったヒト以外の社会性のある動物と異なり、非血縁個体同士の協力も可能だ。この非血縁個体同士の協力こそが、ヒトが他の動物に比べ圧倒的な成功を手にした要因だろうと市橋は推察している。
冒頭で紹介した人工的にRNAを作り、進化を促した実験の話に戻ろう。市橋が作ったRNAが私たちヒトのような高度な生命へと進化をしなかったのはなぜか? その理由は人工RNAでは、生物の進化に欠かせない協力関係を持たせることができなかったからだと市橋は述べる。
あらゆる生物は進化し、複雑化することにより、より単純な生物との競争を避けることができるようになる。細菌は真核生物へと進化することにより、細菌間の競争にさらされることがなくなる。真核生物は多細胞生物へと進化することにより、真核生物間の競争にさらされることがなくなる。そして、こうした進化への鍵こそが協力関係なのである。
私たちヒトはもはや細菌と競い合うことはない。腸内細菌などの存在からも分かるように、互いに排除することなく共生している。協力こそが、私たちを進化のより高いステージへと導くものである。こうした生命進化史の真実を理解することこそが、世界中に蔓延する分断を防ぎ、協調ある社会を築くための第一歩となるのではないだろうか。
2014年2月、ソチオリンピックの興奮冷めやらぬ世界に、衝撃のニュースが駆け巡った。ロシアがウクライナ領のクリミアに武力侵攻し、これを力ずくで併合してしまったというのである。こうしたロシアの行動は当然ながら国連憲章をはじめとした国際法に違反するものであり、世界中の多くの国々はその行為の正統性を認めていない。だが、2021年現在に至っても、ロシアはウクライナに対してクリミア半島を返還する意思をまったく示しておらず、クリミアでのインフラ整備を進めるなど、実効支配を強める行動をとっている。
かつてはチベットや東トルキスタンに武力侵攻した中国でさえ、近年はそうした軍事行動を控えている。そうした中、これほど大胆な武力侵攻を行ったロシアに対して欧米諸国が警戒を強めるのも無理はない。また、ロシアの強権的行動はクリミア侵攻に留まるものではなかった。それ以外でも、ロシアはウクライナ南東部のドンバス地方に民兵を侵入させるなど軍事介入を行っているが、その紛争は現在に至っても終結していない。さらにロシアには、2016年のアメリカ大統領選挙に介入したという疑惑もあり、それも欧米からの疑念を深める根拠の一つとなっている。
こうしたロシアの振る舞いは一見傍若無人に見えるが、実は彼らなりの考えに基づくものであると、本書の著者である小泉悠は指摘する。欧米から見れば明らかに加害者の立場に立つように見えるロシアだが、彼ら自身は自らを被害者と認識しているというのである。
2000年代半ばの旧ソ連諸国では、グルジアのバラ革命(2003年)、ウクライナのオレンジ革命(2004年)、キルギスタンのチューリップ革命(2005年)といった民主化の動きが、雪崩を打つように起こった。こうした民主化の流れは欧米諸国から見れば望ましいことだったが、ロシアの見方は異なると小泉は指摘する。ロシアでは、こうした一連の民主化の動きはアメリカなどによる謀略によって引き起こされたと一般的には考えられているというのである。
ロシアの政治家や軍人が共有する、こうした陰謀論的世界観は、何ら根拠があるものではない。だが、ロシアのリーダーであるプーチン大統領自身も2000年代に旧ソ連諸国で生じた民主化や、2010年代に中東諸国で発生した「アラブの春」はアメリカの謀略であると示唆する発言をしている。アメリカは自分に従わない国に対して、「見えない戦争」を仕掛けているというのである。
プーチン大統領の主張を受け入れるならば、近年におけるロシアの一連の行動は、侵略ではなく、むしろ自衛のためのものだと言える。もちろん、普段欧米発のニュースに親しんでいる私たちには、そうしたロシアの主張は不合理なものに聞こえるだろう。だが、歴史を振り返ってみると、ロシアの主張も必ずしも荒唐無稽ではないことがよく分かる。
1920年代、第一次世界大戦において戦勝国となった日本は、国際社会において存在感を強めていた。そうした日本の立場が一転するのは、1931年に満州事変が勃発してからである。事件が中国によって国際連盟に提訴された結果、日本は世界中から問責非難される立場に立たされてしまった。追い詰められた日本は国際連盟を脱退し、世界から孤立する道を歩んでいくこととなる。
今日、満州事変が関東軍による謀略によって引き起こされたものであると知っている私たちから見ると、こうした日本の行動は無謀なものであると映る。だが、当時の日本国民はそうした背景は知らず、むしろ自分たちは世界から差別、迫害されていると感じていたのである。立場によって、物の見え方は変わる。ロシアの側から見た世界を理解しようとする際に、本書は極めて有益な一冊であると言えるだろう。
本書のタイトル『戦争まで』の戦争とは、具体的には太平洋戦争のことを指す。そしてサブタイトルに「歴史を決めた交渉と日本の失敗」とあるように、太平洋戦争に至るまでの交渉事を再検討し、戦争回避の可能性を探るのが本書の主題である。
本書の著者の加藤陽子は、太平洋戦争回避のチャンスは3回あったと指摘する。その1回目の機会は、1931年9月に勃発した満州事変に対し、国際連盟によって派遣されたリットン調査団が作成した報告書への対応にあった。当時の日本の新聞は、「支那側狂喜」などとリットン報告書に対し中国側が全面的に賛同しているかのような報道を行った。だが、実際のところ中国側の多くの反応は、リットン報告書を日本寄りすぎると厳しく批判するものであり、新聞の報道内容は不正確なものだった。
また、報告書をきちんと読めば、リットンらが必ずしも中国側に肩入れしておらず、日本の立場にも配慮したものであったことがわかると加藤は述べる。だが、当時リットン報告書の全訳は存在しており、日本国民ならだれでも手軽に読むことができる環境にあったにもかかわらず、それを冷静に読んで、建設的な議論を展開していくような流れは生まれなかった。
このような国民の反応を無知と断ずるのはたやすい。だが、現代の我々は満州事変が謀略で開始されたと知っているが、当時の国民はそのようなことは知らないことに注意を向ける必要がある。日本側にも非があると理解していれば、日本軍を満鉄線沿線まで撤兵することを受け入れる余地はあるだろうが、自分たちは悪くないと思っていては、それを受け入れることは難しい。
さらに、満州鉄道に関わる権益は、日露戦争の膨大な犠牲の上に成り立っている。部分的にではあれ、その権益を手放すことには、国内世論の抵抗は相当のものがあったと予想される。
同様のことが2回目の戦争回避のチャンスであった、日独伊三国軍事同盟条約締結のケースについても言える。日独伊三国軍事同盟条約が締結されたのは、1940年9月のことである。すでに第二次世界大戦は1939年9月から始まっていたが、日本は中立の立場をとっていた。ここでドイツと同盟を結び、世界中を敵に回してしまったことが太平洋戦争の敗因にもつながってくるが、なぜ日本はこのような選択をしてしまったのだろうか。
通俗的な理解では、当時ヨーロッパで破竹の快進撃を続けていたドイツの尻馬に、日本政府が乗ろうとしたのだと考えられている。確かに、1940年の時点でドイツは既にオランダやフランスといった国々を打ち破り、残る敵はイギリスのみとなっていた。
だが、加藤によれば日本が条約締結を求めた真意はそこまで浅はかなものではなかったようだ。加藤は海軍の思惑を一例に挙げている。1940年当時、日本の軍事予算の総計は約70億円。その内訳は、陸軍50億円、海軍20億円と陸軍が圧倒的に多かった。日中戦争が1937年に始まっており、40年の時点でも継続中であったことを考えると、陸軍の予算が多いのは自然だが、予算獲得は海軍にとって悩みの種だった。
そこで海軍としてはドイツと同盟を結ぶことにより、ドイツの同盟国であるソ連と日本の関係改善が図れるのではないかという発想が出てくる。大陸からソ連の脅威が消えればこれ以上陸軍に予算を取られることもないし、将来的な日米戦争を想定していると言えば、海軍としては予算要求の大義名分も立つというわけである。
このように、歴史をていねいにひも解いていくと、日本が決して非合理的に戦争への道を歩んでいったのではないことが分かる。同じような過ちを繰り返さないためにも、私たちは通説ではなく、こうした最新の研究に裏打ちされた歴史を学ばなければならないのではないだろうか。
本書の著者ダニエル・カーネマンは行動経済学者であり、心理学の専門家でもある。2002年にはノーベル経済学賞も受賞しており、行動経済学の分野では世界的第一人者と言えるだろう。本書では彼のこれまでの研究が縦横無尽に駆使され、人間の心の働きの核心に迫っている。
カーネマンは、私たちの脳の中には2つのシステムがあると指摘している。彼はそれをシステム1、システム2と分類して呼んでいる。システム1とは、私たちの心の中で、ほとんど努力をすることなく、自動的に高速で働くような動きを意味する。これは無意識的に、コントロールなく動くものでもある。
それに対してシステム2とは、複雑な計算に取り組むときなど、意識的に頭を使うときに働く心の動きである。システム2とシステム1の大きな違いは、システム2を働かせるときは、必ず注意力を要することにある。システム2は、システム1のように無意識的に働くことはない。
日常生活を過ごしているとき、ほとんどの時間作動しているのはシステム1のほうである。私たちが特に意識する必要もなく、自動的に印象や感覚を感じているのは、システム1の働きのおかげと言える。システム2が主役となるのは、日常生活の中で立ち止まって、改めて考えてみるときだけである。複雑なものごとを判断するときなどには、システム1の能力だけで対応することはできない。システム2はシステム1に比べて働くスピードは遅いが、抽象的な思考などはシステム2の助けなしにはできないのだ。
普段の生活において、主役となるのはシステム1である。システム1は無意識的に、自動運転で作動するため、行動するときにいちいち判断をする必要がない。私たちが道を歩いているとき、ほとんどの時間はシステム1の働きによって、何も考えずに歩いていくことができる。システム2の出番は、足元が悪く転ぶ危険のあるときや、暗い夜道を歩くときのみである。これらの場合は注意が必要だから、システム2が主導権を取ることになる。慣れ親しんだ状況ではシステム1、注意を要する場面ではシステム2と分担ができているところが、人間の脳の優れたところなのである。
このように、日常生活においては極めて効率的に協働している私たちの脳のメカニズムだが、社会的な問題が起きた場合には、この優れたシステムがかえって仇となってしまうケースがある。そうした具体例として、カーネマンは1989年に起きたエイラー事件を挙げている。
エイラー事件のエイラーとは、リンゴの生長をコントロールして見栄えをよくするために使われる化学物質の名称のことである。当時、この化学物質は正規の許可を得てリンゴに散布されていたが、あるときネズミにこの物質を大量に摂取させたところ、ガン性腫瘍が発生したというニュースが報道された。そして、この報告をきっかけにしてパニックが起き、リンゴの売り上げが激減してしまった。
後の調査で、エイラーの発ガン物質としての危険性は極めて小さいことが分かった。そのため、現在では誰でも安心してリンゴを食べているが、パニックによって当時のリンゴ農家が被ったダメージは計り知れない。こうしたパニックは、私たちの脳内のシステム1の作用によって生じるものである。システム1は無意識的に作動するため便利だが、感情的になったり、偏見に陥りやすいという欠点がある。そのため社会問題を考える際には、システム2によってシステム1の判断を抑え、冷静になって物事を判断しなければならないのである。
このエイラー事件以外にも、本書には数多くの具体的な事例が紹介されている。人間の心のメカニズムに興味がある方に、ぜひおすすめしたい一冊だ。
近年、日本で政治哲学が注目されるようになったきっかけは、やはり何といってもハーバード大学のマイケル・サンデル教授による『これからの「正義」の話をしよう』が、哲学書としては異例の60万部ものベストセラーになったことが大きいだろう。そのサンデルの政治的立場が、本書で解説されているコミュニタリアニズムである。
サンデルはまずコミュニタリアニズムの優れた面を解説する前に、現代の政治哲学を代表するいくつかの立場について解説し、その問題点を指摘している。サンデルが第一に論敵として検討する政治的立場は、功利主義(utilitarianism)である。
功利主義は一般的に18世紀のイギリスの哲学者、ジェレミー・ベンサムが創始者であると考えられている。功利主義では人間の「喜び」を「効用(utility)」と考え、その最大化を追求する。功利主義の思想が「最大多数の最大幸福の追求」と要約されるのは、そのためである。
現代の経済学では効用という概念を重視するため、功利主義は経済学的思考によく馴染む。だが、サンデルは功利主義には致命的な欠陥が存在するのではないかと指摘する。
サンデルが功利主義の問題点を指摘するために挙げるのが、19世紀にイギリスで起きたミニョネット号事件の例である。1884年、イギリスからオーストラリアに向けて航行していたミニョネット号が難破した。船長を含め4人の乗組員は救命艇で脱出したものの、救出されるまで約一か月近く海上を漂流することとなった。食料は底をつき、いよいよ飢餓状態が極まった船長トーマス・ダドリーは、一番衰弱していた17歳の見習いリチャード・パーカーを殺して、残りの三人の食料とした。
功利主義の観点から言えば、一人を犠牲として三人が助かったのだから、船長の決断は正当化される。だが、サンデルは私たちの多くは常識的に考えて、こうした船長の判断に違和感を覚えるのではないかと説く。いかに命が救われるためとはいえ、殺人はやはり誤りであると考えるサンデルの意見に同意する人は多いだろう。
サンデルは功利主義のみならず、アメリカの政治思想の主流と言えるリベラリズムにも、その批判の矛先を向ける。ここでサンデルが具体例として挙げるのは、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)についてである。アファーマティブ・アクションとは、黒人系やヒスパニック系などの差別されてきた人たちを、大学の入学試験などで有利に扱うことである。リベラリストはこうした措置を当然のものと考えるが、サンデルは大学の意思だけで入学の選考基準を自由に決めるという考え方には、恣意性が潜むのではないかと指摘するのだ。
功利主義やリベラリズムを批判するサンデルが評価するのは、コミュニタリアニズムという考え方である。コミュニタリアニズムでは個々人の価値観に干渉しない従来の政治思想と異なり、美徳を養い、共通善を追求することが生きていく上での重要な目標となる。だが、さまざまな価値観が乱立する中で、共通善を確立することなど可能なのだろうか?
そこで重要になってくるのが対話なのだとサンデルは述べる。異なる考えを持った人々の間でも、実例などを挙げながら辛抱強く対話を重ねれば、より良い答えに到達できるというのがサンデルの考えだ。サンデルはこうした対話のプロセスを、「弁証法」と表現する。アメリカのみならず、世界中で政治的立場による分断が深刻化している昨今、サンデルのように対話を重んじる思想はますます重要なものとなっていくに違いない。
なかなか解決の糸口の見えないCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の拡大。その影響は、世界経済にも深刻な打撃を与えている。リーマン・ショック以来の世界的大不況に立ち向かうために、私たちはどうすればいいのだろうか。
不況が生じた際に、政府がとるべきマクロ経済政策は、金融政策と財政政策である。政府が適切なマクロ経済政策を遂行することは、国民の生活に大きな影響を及ぼす。本書の著者デヴィッド・スタックラーとサンジェイ・バスは、不況時に適切な経済政策が行われるか否かが、国民の健康にまで影響を及ぼすことを突き止めた。本書はその研究成果を一般向けに解説したものである。
政策の効果を測定するためにスタックラーとバスが採用した方法は、RCT(ランダム化比較試験)である。RCTとは対象をランダムに選び、施策を行うグループと行わないグループに分け、結果を比較するという実験方法である。近年、医学などの分野で、薬の効果を測定するにあたって、RCTは極めて大きな役割を果たすようになってきている。
ただ、薬の治験のように実験環境が厳密にコントロールされているような試験を、経済政策の効果測定に応用するのは現実的ではない。そこで、スタックラーとバスはRCTに近い結果が得られる自然実験(natural experiment)を、経済政策の効果を測定するものとして採用した。これは、効果を測定したいと思っている状況に極めて似たケースを過去の歴史のなかから探してくるという方法である。本書の場合で言えば、同じ不況に巻き込まれた地域で、異なる政府が異なる政策を実施したケースを分析し、政策の効果を測定することになる。
具体的な例を挙げてみよう。1929年のウォール街大暴落に端を発する世界恐慌では、アメリカのルーズベルト大統領が経済政策としてニューディール政策を行った。これは雇用の創出やセーフティネットの強化を重視する政策であり、反緊縮的な政策であると言える。だが、これらの政策は全米各州で均一に実施されたわけではない。実施状況は、各州によって差のあるものだった。スタックラーとバスはこれを自然実験の好機ととらえ、ニューディール政策が国民の健康状態にどのような影響を及ぼすのか分析した。すると、ニューディール政策を積極的に採用した州では州民の健康状態が改善したが、消極的だった州ではそうはならなかったことがわかった。緊縮政策は、国民の健康にも確実に影響を及ぼすのである。
スタックラーとバスが研究を重ねた結果わかってきたのは、健康にとって本当に危険なのは不況それ自体ではなく、間違った緊縮政策だということである。2008年のリーマン・ショックによって生じた世界的大不況の際には、スウェーデン、アイスランド、デンマークといった国々が経済的に大きな打撃を受けた。だが、それらの国では緊縮政策などは採用されず、むしろセーフティネットの強化といった反緊縮的な政策が採用されたため、人々の健康状態が悪化することはなかった。アイスランドなどでは、むしろリーマン・ショックの後のほうが国民の健康状態が改善したのである。
反対に、緊縮政策を採用した国ではどうなったであろうか? 緊縮政策を採用したギリシャは、リーマン・ショック以前にはヨーロッパで最も自殺率が低い国だった。だが、2007年以降には自殺が急増し、2012年までに自殺率が以前の倍となる結果となってしまったのである。
このように、不況にあたっては緊縮政策を採用するか否かが、国民の生命に直接関わる。私たちは自らの命を守るためにも、不況時には反緊縮的な政策を採る政治家を選ばなくてはならないのである。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大が止まらない。アメリカでは、死亡者数が40万人を超えた。第二次世界大戦におけるアメリカの死亡者が約40万人であったことを考えると、これは驚くべき数字である。
感染が収束しないのは、アメリカだけではない。第一波はしのいだものの、日本でもまだまだ安心できるという状況ではない。本書の著者の河岡義裕はウイルス学の世界的権威で、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議のメンバーとして、第一波の収束に貢献した人物でもある。現在でも河岡はCOVID-19の対策に関わっており極めて多忙なため、大宅壮一ノンフィクション賞受賞者である実力派ノンフィクション作家の河合香織が共著者として、本書の執筆をサポートしている。
20世紀以降、人類は計5回のパンデミックを経験してきた。そのうち、最初の3回のパンデミックは1918年のスペイン風邪、1957年のアジア風邪、1968年のホンコン風邪といったように、日本語では「風邪」と呼ばれてきた。だが、これらはいずれもインフルエンザウイルスが原因となって生じたものである。スペイン風邪では、世界で2000万人から4000万人が、アジア風邪では約200万人、ホンコン風邪では約50万人もの人々が亡くなった。いずれも驚くべき数字だが、幸いなことにホンコン風邪の流行以降、世界では40年以上パンデミックが起こることはなかった。
もう、二度とパンデミックが起こることはないのではないかという楽観的なムードを打ち破ったのが、2009年の新型インフルエンザによるパンデミックである。このときの死者は約18500人とこれまでのパンデミックより低い数字に抑えられたとはいえ、パンデミックはいずれ必ず起こるものだということを、私たちに知らしめた事件であった。
そして今、私たちはCOVID-19の脅威に直面している。だが、どうしてこのウイルスはここまで世界的に拡大してしまったのだろうか? ネットなどではまことしやかに、COVID-19は武漢のウイルス研究所で人工的に合成されたものであり、それが流出したのだと語られている。だが、河岡はCOVID-19が人為的に作られた可能性は極めて低いと語る。河岡によれば、元のウイルスと同程度、もしくは弱毒化したウイルスを作ることは、技術的にそれほど困難なことではないという。その一方で、ウイルスの病原性を高めるというのは非常に難しい。そもそも、ウイルスとは自然環境の中で既に最適化されており、それをさらに強毒化するのは、ほとんど不可能なのだ。世界で初めて人工的にインフルエンザウイルスを合成することに成功した実績を持つ河岡の説明は極めて明快であり、説得力を持つものだ。
COVID-19のワクチン開発に成功しても、それが日本中に行き渡るにはかなりの時間がかかりそうだ。それでは、今現在私たちができることは何もないのだろうか? 河岡は何よりもまず、COVID-19の感染者を特別視することをやめるのが大切だと説く。
ウイルスは人を選ぶものではないため、誰でも感染する可能性がある。夜の盛り場など人と接触する場所を避けることはできても、医療従事者や公共交通機関の職員などといったエッセンシャル・ワーカーは人との接触を避けることはできない。また、易感染性(病気にかかりやすい)の遺伝子を持った人は、そうでない人に比べCOVID-19にかかりやすい可能性もある。感染者をバッシングすることは、感染経路の隠蔽にもつながる。COVID-19の克服のために私たちがまずできることは、感染者に対して寛容な社会を作ることではないだろうか。
米中対立が深刻化している。2020年8月、アメリカのトランプ前大統領は、安全保障上の脅威だとして、動画投稿アプリTikTokを運営するバイトダンス社との取引を禁止する大統領令に署名した。その後、アメリカ政府はTikTokの利用禁止措置の発動を当面見送ることとしたが、バイデン政権が誕生した今も、米中間の緊張は依然として緩和されていない。
本書の著者であるピーター・ナヴァロは、こうした中国脅威論に対して、「米中戦争は不可避だ」と考えるのは、大きな間違いであると断言する。統計学上のデータを基にしたナヴァロの分析によれば、1500年以降、世界史において中国のような新興勢力がアメリカのような既存の覇権国と対決した例は15件あるという。そして、そのうち11件については、軍事的な衝突へと発展している。だが、残り4件では、軍事衝突には至っていない。すなわち、歴史上、覇権国と新興国が対峙した場合、70%の確率で戦争へと発展しているが、残り30%の確率で軍事衝突を回避している。それならば、どのようにして私たちは今後、戦争を回避すればいいのかというのが、本書の主題である。
ナヴァロは対立を回避するには、相手を正しく理解することが重要であると説く。中国が日本のような平和主義の国家なら、ことさらアメリカが事を構える必要はないというのである。では、実際に中国は平和主義的な国家なのだろうか?
それにはまず、過去の歴史を振り返ってみることが重要だ。1949年に中華人民共和国が建国して以来の歴史を概観することによって、中国が平和主義であるかどうかが分かるだろう。
建国直後の1950年、中国は早くもチベットへの武力侵攻を開始する。ほとんど近代的な軍隊を持たないチベットはあっという間に制圧されてしまうが、中国への反発は根強く残った。1959年にはチベットの民衆が蜂起し、チベット動乱が勃発するが、やはり人民解放軍の圧倒的な火力の前には敵わず、指導者のダライ・ラマ14世は支持者と共にインドへと亡命。チベットの独立を求める彼らは、2020年現在の今も祖国に帰れずにいる。
その後中国は、チベットに続いて東トルキスタンにも侵攻、これを併合した。かつての東トルキスタンを含む、現在の新疆ウイグル自治区でもチベットと同様に、半世紀以上にわたり独立運動の灯は絶えないが、中国政府に徹底的に弾圧され続けている。こうしたチベットと新疆ウイグル自治区を合わせた面積は、中国の国土の30%を占めるほどの広さである。
チベットと東トルキスタンを併合した中国は、それで満足することはなかった。1963年、ダライ・ラマ14世の亡命を受け入れたことによって対立を深めたインドに対して、中国はついに侵攻を開始する。戦闘は人民解放軍の圧勝に終わり、中国は再びその領土を広げた。インドには中国に対する根深い不信感が残ったが、中国の圧倒的な武力を前に、為す術がなかった。
このように、中華人民共和国の歴史は他国への侵略の歴史であったといっても過言ではない。日本のような平和主義の国家とは、根本的に理念が異なる体制である。
中国は膨張主義的国家である。これは間違いない。では、そのような中国とアメリカ、そして日本はどのようにして戦争を回避すればいいのだろうか?
それに対するナヴァロの提案は、極めてシンプルである。アメリカとアジア諸国の同盟の深化。それが、ナヴァロの考える戦争回避のための処方箋である。日米同盟だけではなく、かつて中華人民共和国と戦火を交えたインド、ベトナムといった国々とも、関係を強化することが大切だ。いくら中国が強大だからといって、世界中を敵に回して戦争をすることはできない。中国の実力を正確に見極め、国際協調主義に基づいて、積極的にアジア諸国と外交関係を緊密化すること。日本の平和を守る道は、そこにこそあるのではないだろうか。
史上初めて、モンゴル帝国はユーラシア大陸の全域を制覇した。そして、その支配の安定のもと、商業活動はそれまでにない繁栄を極めた。中でも顕著だったのは、貨幣制度の発達である。紙幣の普及は、その最たるものと言える。それまでにも、中国に紙幣というものは存在した。だが、この時代にこれほど紙幣が普及した背景には、モンゴル帝国が発行した紙幣と銀との交換を保証したことがある。紙幣そのものには貴金属のような値打ちがないため、その価値を保証する強力な権力が必要だったのだ。
だが、そうしたモンゴル帝国の繁栄も、14世紀に入ると陰りを見せ始める。世界的なペストの流行や、気候の寒冷化による不作などによって、モンゴル帝国は徐々に弱体化していった。
その隙をついて台頭してきたのが、明の太祖朱元璋である。南京を拠点とした朱元璋は、1368年、モンゴル帝国を万里の長城の北に駆逐することに成功する。
こうして時代はモンゴル帝国から明へと移り変わったが、中国経済はモンゴル時代と比べ、大きく停滞することとなってしまう。その原因は、明の貨幣制度にあった。紙幣中心だったモンゴル帝国と異なり明では、なるべく貨幣を介在させずに政府の財政経済活動を実現しようとする現物主義へと舵を切ったのである。もちろん、現物主義と言っても、明で貨幣が全廃されてしまったわけではない。モンゴル時代同様に「大明宝鈔」という紙幣も発行されていた。だが、それらはあくまで現物主義を補完するものに過ぎず、モンゴル時代の紙幣のような、信頼のおける貨幣ではなかった。
政府の法定通貨が当てにならないなか、民間では貨幣不足を乗り切るために、銀の使用が広まっていった。もちろん、それらは違法行為ではあるが、高まる貨幣需要を乗り切るための窮余の一策として仕方なかった。こうして明では銀の需要が高まる一方であったが、新大陸から産出した銀が、大航海時代のおかげで明に流入し、また当時、隣国の日本でも銀山の開発が盛んだったため、どうにか十分な量の銀の確保に成功した。こうして、明の経済は安定と発展の時代を迎えた。
しかし、繁栄を続けた明にも、やがて落日の時が来る。ジュシェン(女真)のリーダーであるヌルハチが1583年に挙兵すると、約30年かけてジュシェンを統一し、清の前身となる後金を1616年に建国した。
ジュシェンという少数民族が大国である明を打倒し、清を建国できたのには理由がある。17世紀前半、世界中に異常気象や飢饉が頻発し、新大陸の銀輸出が激減してしまったため、明の経済も大きく停滞していた。清の台頭には、そうした明の政治的・経済的混乱に助けられた部分が多分にあるのだ。
明から清へと王朝が交代しても、中国の貨幣の中心は銀だった。明末期に外国からの銀輸入が減少していたことに加え、第4代皇帝である康熙帝が節倹を重んじたため、清の経済は深刻なデフレへと陥ってしまった。行き詰った康熙帝は180度政策の方向を転換し、長年続いていた海禁を解き、海外貿易に力を入れるようになる。当初の貿易相手は東南アジアやインドだったが、とりわけ重要だったのは、西洋諸国との貿易である。清の特産品である茶を西洋諸国に売り、その対価として大量の銀を得ることによって、清はデフレ脱却に成功した。こうして清は繁栄し、その統治を盤石のものとしたのである。
本書は中国における明・清の時代の経済を解説したものだが、国や地域、時代を問わず、貨幣の流通をめぐる政府の取り組みが、社会の発展や安定にとって極めて重要な役割をもつことがよくわかる。経済の観点から中国の歴史を学んでみたい方におすすめの一冊だ。
近年、中国やロシアといった権威主義体制の国家に対し、アメリカをはじめとした民主主義国家は警戒感を強めている。だが、民主主義の国の代表のように見られるアメリカにおいても、国内に問題が山積している。人種差別問題への抗議のデモや集会は、毎日のように続いている。ネットに目を向けてみれば、真偽不明のフェイクニュースが溢れ、何が正しいことなのか見極めることが非常に困難になっている。
本書の著者、ジョセフ・ヒースは今日の政治が抱える問題を克服するために、古代アテネに立ち戻って考えることを提案する。民主主義が発明されたといわれる古代アテネにおいても、それに懐疑的な立場の論者は多くいた。ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった古代アテネの偉大な哲学者たちは皆、民主主義体制に強く反対をしていた。彼らは民主主義体制が抱える不安定さを、その段階で既に見抜いていたのだ。
プラトンら哲学者が警戒していたのは、民主主義に付き物のデマゴーグの存在である。デマゴーグは無知な大衆の弱さにつけこみ、嘘の情報や陰謀論によって恐怖、怒り、偏見といった感情を煽り、間違った政策へと人々を扇動していく。民主主義はこうしたデマゴーグにとって有利な制度であり、彼らを抑止する抜本的な手段も存在しないため、哲学者たちは民主主義に反対したのである。
このように、民主主義とはそのシステムに致命的な脆弱性を抱えたものである。そしてさらに、21世紀になって世界中に普及したインターネットが、これまで以上にデマゴーグに活躍の場を与えている。ヒースは、blogが流行していた時代はまだよかったという。SNSの登場が、フェイクニュースや陰謀論の拡散に決定的な影響を与えた。断片的な情報の拡散に有利なSNSは、blogのように長い文章を読み、熟慮する人々をネット上から駆逐してしまったのである。
ヒースは陰謀論の典型として『シオン賢者の議定書』を紹介している。『シオン賢者の議定書』は、1903年に発表された反ユダヤ主義の小冊子である。その内容は荒唐無稽で、ユダヤ人たちが世界征服の陰謀を密かに企てているというものである。『シオン賢者の議定書』は、1921年の段階でイギリスの『タイムズ』紙の記事によって、まったくの捏造であることが暴露された。だが、驚くべきことにほとんどの人々はその記事を信じず、ユダヤ人による世界征服の陰謀論は拡散を続けた。そして、それはやがてナチスによるユダヤ人の虐殺を招くのである。
現代はインターネットがあるため、『シオン賢者の議定書』が広まった時代と比べ、陰謀論はより速く、広く拡散するようになっている。このままでは、民主主義は陰謀論とフェイクニュースの氾濫によって、衰退していってしまうだろう。私たちに、この危機を乗り越える解決策はあるのだろうか?
ヒースは民主主義を復活させるには、私たちのコミュニケーションを今よりゆっくりとしたものにする必要があると考え、「スロー・ポリティクス」という概念を提唱している。ネットで見た情報に脊髄反射的に反応して拡散するのではなく、一旦停止し、情報を吟味することが大切だ。ネットで流れてきた情報をファクトチェックし、真偽を見極めることを習慣化すれば、陰謀論の拡散に加担してしまうこともなくなる。
これまで、私たちの政治的なコミュニケーションは加速を続け、今ではすっかり「ファスト・ポリティクス」が主流になってしまった。だが、そうした加速化したコミュニケーションには、本来必要な相互理解や、熟慮といったものが存在しない。今こそ私たちは、従来のファスト・ポリティクスを乗り越え、スロー・ポリティクスへと移行することが求められているのである。
2010年、アメリカの政治哲学者マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』が60万部を超えるベストセラーとなり、世間では大きな話題となった。難解な哲学の本がこれだけ売れるのは、異例中の異例のことである。
これだけ大きな話題となったのは、同時期にサンデルがNHKのテレビ番組に出演していたことにも影響されているだろうが、同時に「正義論」という日本人にはなじみの薄いテーマが主題となっていたことにも一因があるだろう。本書の著者の仲正は、日本人とアメリカ人では、「正義」という言葉の使い方が大きく異なると指摘する。
日本で正義という言葉が使われる場合、月光仮面のような「正義の味方」を連想することが多いだろう。そうした正義の味方は自分の力を行使する際、いちいちそれが客観的にみて正しいか、法律に則っているかなどということは検討しない。ただ、主観的に自分が正しいと信じる価値観に基づいて行動をするだけである。
それに対して、英語のjusticeという単語には、正義という意味のみならず、「司法」「公正」といった意味がある。ただ主観的に自分が正しいと思ったことを行うのは、アメリカでは正義とは考えられない。そうではなくスポーツなどの審判がするように、物事を公平かつ公正に取り扱うことを、アメリカでは正義と言うのである。「公正さ」こそが、正義の基盤なのだ。
だが、そう言っただけではまだ抽象的で、何が具体的に正義なのかがよく分からない。そこで、アメリカの哲学者ジョン・ロールズは正義を2つの原理に定式化した。
まず、正義の第一原理では、人々に基本的自由が平等に保障される。これは、日本国憲法における「基本的人権」に通じる概念である。ロールズは、保障されるべき「基本的諸自由」を、具体的にリスト化している。①「政治的自由」(投票権や公職就任権)、②「言論及び集会の自由」、③「良心の自由」と「思想の自由」、④心理的圧迫と身体への暴行からの自由を含む人身の自由、⑤「個人的財産を保有する権利」、⑥法の支配の概念によって限定される「恣意的な逮捕・押収からの自由」。正義の二原理では、第一原理が第二原理に優先するので、これらの自由が保障されることが、ロールズの考える民主主義の最低条件ということになる。
正義の第二原理では、こうした諸自由が保障された上で、社会的にどこまで経済的不平等が許容されるかが問われることになる。私たちに許容される格差の程度を決めることは難しい。完全に市場の原理にまかせ、自由放任主義的な経済政策を採用するケースから、徹底した結果の平等を志向する政策まで、その振れ幅には大きなものがある。
そこでロールズが正義の第二原理として提案したのが「格差原理」である。格差原理とは、人々が持って生まれた不平等や格差を、一定の範囲内に収めることを目指す原理である。ロールズは、格差とは社会の中で最も不遇な人たちの権利を改善させる限りにおいてのみ許されると考える。言い換えるなら、最も不遇な人たちの福祉を向上させないような種類の格差は認められないということになる。
こうしたロールズの考えに対しては、リバタリアニズム、コミュニタリアニズムといったさまざまな立場から批判が寄せられている。そうした批判の中には鋭いものもあり、ロールズ自身も寄せられた批判に応じて、自身の議論に修正を図っている。しかしながら、現代の正義論を考えるうえで、ロールズの提示した正義の二原理は、あらゆる議論の原点となるものである。正義論に関心があるのなら、批判するにせよ支持するにせよ、一度はロールズの著書を紐解いてみる必要があるだろう。
現代の国家と異なり、江戸時代、幕府はその天領(直轄地)からしか年貢を取り立てることができなかった。江戸後期、全国の石高は3000万石ほどだったが、そのうち天領の石高はわずか400万石程度に過ぎない。そうしたわずかな歳入で、江戸幕府はいかにして全国を統治することができたのか? そのメカニズムを解き明かしたのが本書である。
開幕当初の江戸幕府の歳入は潤沢なものであった。16世紀以降、日本では多くの鉱山が開発され、金・銀・銅といった貴金属の生産量は飛躍的に向上していた。それらの鉱山は、すべて幕府の直轄であり、そこから得られる利益は皆、幕府のものとなった。こうした豊富な鉱物資源という裏打ちがあったため、幕府はわずかな年貢収入しかないながら、全国統治が可能となったのである。
だが、三代将軍家光の時代以降、鉱山収入は減少に転じる。鉱物資源には限りがあるため、採りつくしてしまえば、それ以上の収入は見込めない。幕府は何とかして鉱山開発ができないかと試行錯誤するが、日本で再び金や銀の生産量が増大するには、昭和初期まで待たなければならなかった。
鉱山収入の減少によって、幕府の財政は17世紀半ばには赤字に転落した。五代将軍綱吉の時代になると、幕府の歳入は年120万両だったのに対し、歳出は約130万両となってしまった。年にして約10万両の赤字である。幕府の財政は深刻化の一途をたどっていた。ここに至って、幕府は抜本的な財政改革を行うことになる。それが貨幣の改鋳である。
この貨幣の改鋳を指揮したのが、勘定頭差添役の荻原重秀である。それまで江戸市中に流通していた慶長小判の金の含有率は約86%。そこで新しく元禄小判を改鋳し、その金の含有率を約57%とした。言い換えるなら、慶長小判2枚から元禄小判が3枚鋳造できることになる。こうして幕府は莫大な額の貨幣発行益を得ることになり、荻原重秀は江戸幕府の財政再建に成功した。
華々しい成果を上げた荻原重秀の貨幣改鋳だが、このように貨幣の発行量を増やすことによって経済が良くなるなどとは、信じられないという人も多いかもしれない。また、急激に貨幣の発行量を増やせば、インフレーションを起こすのではないかという疑念を持つ人もいるだろう。結果から言えば、元禄の改鋳によって、急激なインフレは起きなかった。インフレ率は平均して年率3%程度の上昇に留まり、市民生活に混乱は生じなかった。現代のマクロ経済政策における望ましいインフレ率は、年率2%程度と考えられている。元禄の改鋳は世間にマイルドなインフレをもたらし、江戸の社会はこれまでにない繁栄の時代を迎えることとなった。
元禄の改鋳の成功に気をよくした幕府は、再度の改鋳を試みることを決めた。それが宝永の改鋳である。だが、今度は元禄期のようにうまくはいかなかった。1710年代に入ると、急激なインフレが生じるようになったのである。飢饉や天災によって財やサービスの供給が限られているところで貨幣の発行量を増やしてしまったのが、大幅なインフレが起きた原因である。江戸の経済は大混乱に陥り、宝永の改鋳は失敗した。
現代でも、減税などの分かりやすいメッセージを含む財政政策への期待は大きいが、貨幣の量をコントロールする金融政策への国民の理解は乏しいようである。だが、江戸時代の経済史を改めて見てみても、金融政策の果たす役割が極めて大きいことがわかる。本書は一般の読者向けに、日本の古代から近世までの経済史を分かりやすく解説している。現代の日本がとるべき経済政策を考えるうえでも、ぜひ参考にしたい一冊である。
2020年4月、世界の数学界に衝撃が走った。京都大学教授の望月新一による宇宙際タイヒミュラー(IUT)理論の論文が、専門誌に受理されたというのである。IUT理論を用いれば、数学の大難問と言われるABC予想の解決も可能となる。そのため、このニュースは世界中で大きな話題となったのだ。
世界的に注目を集めるIUT理論だが、こうして無事専門誌に論文が受理されるまでには、長い道のりがあった。最初に望月がIUT理論の論文を発表したのは2012年。この論文の査読には、実に8年もの歳月がかかったことになる。
これほど異例の査読期間がかかったのには、さまざまな理由がある。まずは、望月論文の桁外れな長さがその理由の一つとして挙げられるだろう。数学の論文は、通常ならせいぜい数ページから数十ページ程度のもの。それが、この論文では500ページを超えるというのだから桁違いである。
無論、ただボリュームがあるだけであれば、多少時間をかければ、それを読み解くことができる数学者は多いだろう。だが、このIUT理論は極めて斬新な理論である。従来の数学とは、まったく視点や概念が異なるものだ。それを正しく理解するには、新しい数学の分野を一から学ぶような忍耐を要する。こうした背景が、査読に極めて長い時間がかかった一因と言えるだろう。
かつてフェルマーの最終定理を証明したアンドリュー・ワイルズは、7年間自分がその問題に取り組んでいることを誰にも話さず、秘密を守りながら証明を完成させた。そのため、IUT理論もそうした秘密主義のもとに研究されていたと想像しがちだが、本書を読めばそうした事実はまったくなかったことがよくわかる。ワイルズと異なり、IUT理論を構築した望月は極めてオープンな性格で、誰にでもアクセスできる形で研究を公開してきた。もちろん、極めて難解な理論のため、それを理解するには本人から詳細なレクチャーを受けることが欠かせない。本書の著者の加藤は望月の友人であり、研究仲間としてIUT理論が生まれる現場に共にいた人物である。数学の啓蒙書の著書も多く、一般向けのIUT理論の解説書の著者として、彼以上の適任者はいないであろう。
ただ、そこまで一般向けにやさしく、かつ明晰に解説をしたとしても、IUT理論が極めて難解な理論であることは変わりない。まず、宇宙際(Inter-universal)という名称自体、極めて独特である。私たちは国際(international)という言葉なら頻繁に使うが、宇宙際とは一体どのようなものだろうか?
突然宇宙という言葉が出てくると、SFのパラレルワールドのようなものを想像してしまうが、宇宙際とはそのようなものを意味する言葉ではない。加藤によればIUT理論における「宇宙」という言葉は、「数学一式の舞台」のことだという。国内だけにとどまらず、いろいろな国を行き来することを「国際」というように、複数の「数学一式の舞台」を自由に行き来することにより、一つの数学的宇宙に閉じこもっていただけでは解けないような問題が解決できるようになるところに、IUT理論の独創性があるのだ。
だが、このように説明を重ねてみても、最先端の数学が話題となっているため、理解しがたい部分があることも事実だろう。そこで本書の理解を助ける心強い味方となるのが、ネット上にアップされている動画コンテンツだ。本書の内容は、2017年10月に行われた数学イベント「MATH POWER 2017」における講演がもととなっているが、その講演の内容がYouTubeに公開されている。【☆注:1】また、出版社による加藤への詳細なインタビュー動画も同様に公開されている。【☆注:2】こうした動画コンテンツも併用し、理解を深めることができるのが本書の強みである。
【☆注:1】abc Conjecture and New Mathematics
https://www.youtube.com/watch?v=fNS7N04DLAQ
【☆注:2】『宇宙と宇宙をつなぐ数学』加藤文元先生インタビュー 第1回「IUT理論の現在地」
https://www.youtube.com/watch?v=pNotF9QaNKM
最近、書店へ行くとタイトルに「地政学」とついた書籍をよく目にする。世間ではちょっとした地政学ブームのようだ。
だが、その一方で、大学には地政学と名のついた学部は無いし、テレビなどで地政学の専門家を目にすることもない。一体、地政学とはどのような学問なのだろうか?
本書は、そうした疑問に明快な答えを与えるものである。地政学の成り立ちから、その発展の歴史、そして現在までが本書の中に網羅されている。
地政学の事実上の創始者は、イギリスの地理学者、H・J・マッキンダーである。マッキンダーは1861年、イギリスのリンカーンシャーで生まれた。マッキンダー自身は地政学という用語を使わなかったが、1904年に彼が英国の王立地理学協会で行った「歴史の地理学的な回転軸」という講演が、世の中に地政学的な考えを広めた画期だったと考えられている。
では、マッキンダーの説いた地政学とは、どのようなものだったのだろうか? マッキンダーは第一次世界大戦を、ランド・パワー(大陸勢力)の国家と、シー・パワー(海洋勢力)の国家の闘争と捉えた。そして、この戦争においては、ランド・パワーの国家とは、具体的にはドイツを、そしてシー・パワーの国家とはイギリス、アメリカ、日本といった国々が想定されていた。
ランド・パワーの国家にとって何より重要なのは、ユーラシア大陸の心臓部(ハートランド)を制することである。ハートランドとは、具体的には今日の東欧の地域を指す。元々地理学者だったマッキンダーは、ランド・パワーの国家にとっては、当時の交通の要衝であった東欧を制することが、死活問題となることを見抜いたのだ。
このマッキンダーによるハートランドの理論を継承したのが、ドイツの地政学者、カール・ハウスホーファーである。1869年にミュンヘンで生まれたハウスホーファーは、軍人(陸軍少将)でありながら、ミュンヘン大学教授としても活躍した人物だ。
そんなハウスホーファーにとって転機となったのが、アドルフ・ヒトラーとの出会いであった。ナチスの副党首ルドルフ・ヘスが、第一次大戦中にハウスホーファーの副官だったことが縁となり、ハウスホーファーはミュンヘン一揆の失敗により収監されていたヒトラーと面会することになる。
ハウスホーファーからハートランドの理論を聞いたヒトラーは、地政学に傾倒するようになっていった。収監中に書かれた彼の著書『我が闘争』を読むと、その影響がよくわかる。東欧を制することが、世界を制することにつながると確信したヒトラーは、やがて実際に東欧の国々へと侵攻していった。
ハウスホーファー自身はナチス党員ではなく、1944年には彼の妻がユダヤ系だったことから、夫婦で強制収容所に収監されている。そして、ハウスホーファーは終戦翌年の1946年に自殺した。だが、そうした背景にもかかわらず、地政学はナチスの侵略を正当化するイデオロギーとなってしまったことから、戦後は顧みられることのない学問となっていった。
こうして現在では学問の世界から姿を消してしまった地政学だが、その戦略的思考は国際政治学や国際関係学といった分野の中に息づいている。国際政治学の中では、勢力均衡(バランス・オブ・パワー)を重視するリアリズムの立場が地政学を継承していると言えるだろう。国際情勢が混迷を極めるなかで、地球全体を一つのものとして、戦略的に捉えるという地政学の考え方は、益々重要なものとなっていくことは間違いない。
歴史とは、私たちの世界観を形作るものである。今日では、世界中の国々でさまざまな歴史観が共有されているが、それらには大きく分けて2つの源流がある。1つはヘーロドトスの『歴史』に源を持つヨーロッパの歴史観。もう1つは、司馬遷の『史記』に源を持つアジアの歴史観である。
ヨーロッパの歴史観の特徴は、宿命的なアジアとの対決と、それからの勝利が主題とされることにある。ヘーロドトスの『歴史』は、全世界を支配するほどの強大な力を持つペルシアに、弱小のギリシア人たちが戦いを挑み、最後に奇跡的に勝利をするという物語である。これが、その後のヨーロッパの歴史観を形作ることになっていった。
ヘーロドトスの『歴史』と並んでヨーロッパ人の世界観を形作ったのが、「ヨハネの黙示録」である。ヨハネの黙示録は聖書の他の福音書のトーンとは非常に異なっており、善の原理と悪の原理(サタン)の戦いという二元論が主題となっている。本書の著者の岡田は、ヨハネの黙示録のこうした主題の背景に、ゾロアスター教からの影響を見ている。善と悪の戦い、そして善の最終的な勝利という構図が、ヨハネの黙示録と極めて類似しているというのだ。こうした善悪二元論の考え方は、ヨーロッパには根強いものであり、近代におけるマルクス主義もその亜流である。
では、司馬遷の『史記』に連なる中国の歴史観とは、どのようなものだろうか? 中国の歴史観はヨーロッパのように外敵との闘い、二元論といったものが主題ではなく、各王朝における皇帝の歴史とその正統性を記述するものである。
戦乱や下剋上が日常で、その合間にわずかな平和が実現する中国では、統治者の正統性にひときわ関心が集まる。後漢の時代(156年)、5000万人もの人口を誇り、繁栄を極めた中国も、184年に黄巾の乱が起こると、大混乱に陥ることになる。黄巾の乱と、それにうち続く内戦によって、中国の人口はなんと5000万人台から400万人台まで激減してしまう。これほどの人口の急激な減少は、人類の歴史上ほとんど例のない出来事である。
この中国史上における一大事であった黄巾の乱だが、その終末論的世界観もゾロアスター教の影響であると岡田は指摘する。14世紀に紅巾の乱を起こし、元を打倒した白蓮教もゾロアスター教系である。ゾロアスター教が世界史に与えた影響には、根深いものがある。
壊滅の危機にあった中国を再び統一し、一つの国家にまとめ上げたのが、遊牧騎馬民族である鮮卑系の李世民であった。唐を建国し、太宗となった李世民は、630年に東トルコ帝国を打ち滅ぼす。こうして李世民は草原の遊牧民たちに対しては天可汗(テングリ・カガン)として、唐においては皇帝として君臨することになる。ユーラシア大陸の東と中央の覇者が、こうしてつながったのである。
唐の時代から強まっていった遊牧民の台頭は、13世紀のチンギス・ハーンの登場によってピークを迎える。シルクロードなどを通じてわずかな交流はあったものの、12世紀までの世界では、アジアとヨーロッパの交流はほとんどなかった。それが、13世紀のモンゴル帝国の出現によって、それまでになかった単一の「世界史」が初めて生み出されたというのが、本書における岡田の主張である。
ヨーロッパ中心史観の西洋史でもなく、アジア中心史観の東洋史でもない、まったく新しい形の遊牧民を中心とした世界史。それが本書の魅力である。本書を読むことを通じて、これまで見たこともないような、新しい歴史の見方をぜひ楽しんでいただきたい。
リベラルの凋落が指摘されて久しい。本書のデータによれば、2011年の時点で、アメリカで保守を自認する人々は全体の41%、それに対しリベラルを自認する人々は21%であり、保守の半分程度しかいない。日本においても、ここ30年、ほとんど与党の地位にあったのは保守政党であり、リベラル政党が政権についていた期間は短い。
本来なら、社会の自由と平等を推進しようとするリベラルの立場に、もっと人気が集まってもよさそうなものである。なぜそうならないのだろうか? この難問に挑んだのが、本書の著者、ジョナサン・ハイトである。
心理学者であるハイトは、まず人間の心のメカニズムを分析する。人間の心は、理性と情動(感情)という2つの部分に分けることができる。古来より、理性と情動の関係については、3つの異なる立場があった。まず、プラトンは理性と情動の関係においては、理性が優越すると考えた。理性が主人の立場であり、情動は召使の立場にすぎないとプラトンは指摘する。それと正反対なのが、イギリスの哲学者、デイヴィッド・ヒュームの考えである。ヒュームは主人の立場にあるのは情動であり、理性はそれに従属するものにすぎないと主張した。そして、それらの考えに対し、理性と情動とは平等な関係にあると考えたのが、アメリカのトーマス・ジェファーソンである。
ハイトは、さまざまな心理学的実験の結果、ヒュームの意見が正しいと結論付ける。心は、乗り手(理性にコントロールされたプロセス)と象(自動的なプロセス)の二つの部分に分かれるが、このうち、主導権を握るのは象の部分なのである。
私たちは何か物事に出会うと、まず感情で判断し、しかる後、理性的に物事を考える。ここから得られる教訓は、もし何か政治的な見解について他人の意見を変えたいのなら、まずは相手の感情に働きかけるべきということである。いきなり相手の理性に働きかけても、ほとんどの場合、その試みは失敗するだろう。
これらの心理学的な知見を基にして、ハイトはさらに考察を進める。アメリカでは、経済的弱者にやさしい政策を推進しているのは、民主党である。だが、それにもかかわらず、貧困層には共和党支持者が多い。その理由についてリベラルは、共和党は貧困層をだまして、自らの党に投票するように誘導しているのだと主張している。だが、本当は地方や労働者階級の有権者は、経済的利害ではなく、道徳的基盤にしたがって投票しているのである。
道徳は、理性よりむしろ情動の部分に属する心の働きである。ハイトは普遍的な道徳の基盤を、<ケア/危害>、<公正/欺瞞>、<忠誠/背信>、<権威/転覆>、<神聖/堕落>、<自由/抑圧>という6つのものに分類した。そして、民主党は<ケア>、<公正>、<自由>といった3つの道徳的価値のみを重んじるが、共和党は6つの道徳的基盤すべてにアピールする戦略を取っているため、より多くの有権者の支持を得ることができていると分析する。
保守が重んじる<権威>、<神聖>といった価値観は、リベラルからはナンセンスに見えるかもしれない。だが、ハイトはそうした一見非合理に見える価値観も、人間の心に集団志向性が含まれることを理解すれば、見え方が変わってくると指摘する。宗教のように非合理的に見えるものであっても、それを通じて集団が団結できるのなら、他集団との競争に役に立つ。そうして集団間の競争に打ち勝ってきた遺伝子が、今日私たちの中に眠っているというわけである。
本書は600ページを超える大著だが、具体的な心理学的実験をベースに議論が進むため、強く引き込まれる。人間の心のメカニズムを理解したいと思っている方に、おすすめできる一冊だ。
2010年、日本でハーバード大学のマイケル・サンデル教授による『これからの「正義」の話をしよう』が出版されると、たちまちベストセラーとなり、60万部を突破した。本が出版される直前に、NHKで「ハーバード白熱教室」というサンデルの番組が放映されていた影響も大きいとはいえ、難解な哲学の本にこれだけ注目が集まるというのは、異例のことである。
ここまで政治哲学に関心が高まった背景として、冷戦崩壊以降、それまで自明視されてきた価値観が揺らぎ、世界が混とんとしてきたことが挙げられるだろう。自由主義陣営の西側諸国と社会主義体制の東側諸国という、比較的単純な対立の構造にあった世界は、今ではすっかり複雑なものとなってしまった。そんな中で、新しい正義の基準を知りたいと思った人々がサンデルの本を手に取ってみたであろうことは想像に難くない。
本書の著者の神島は、サンデルを含めた現代正義論の系譜を、古典的リベラリズムに遡って説き起こす。古典的リベラリズムにおいて最も重要な人物は、イギリスの哲学者、ジョン・ロックである。ロックはその著書である『統治二論』の中で、私たちの「生命」「自由」「財産」といったものは、何者によっても侵されることのない人間の固有の権利であると主張した。
ロックが説いたのは、基本的人権だけではない。宗教的寛容の大切さも、ロックは主張している。ヨーロッパに信教の自由という概念が生まれたのは、三十年戦争以降のことである。ロックの生きた時代には、まだ信教の自由は世間に浸透していなかったため、彼自身プロテスタントとして国王の迫害から逃れ、オランダに亡命している。ロックにとって宗教的寛容は他人事ではなかったのである。
こうした古典的リベラリズムの立場を現代に受け継いでいるのが、リバタリアニズムだ。リバタリアニズムの代表的な思想家として挙げられるのは、ロバート・ノージックである。ノージックは古典的リベラリズムが重視した基本的人権や宗教的寛容を守るために、「最小国家」が必要であると説く。
最小国家とは、私たちが一般にイメージする国家とは異なるものである。それは、私たちを他人からの暴力や盗みといった攻撃から守るためだけに存在する国家のことである。言い換えるなら、国家が保護してくれるのは、私たちの生命や財産の所有権のみである。今日ある国家の主要な機能である、税制度を通じた富の再配分などはノージックから見れば、不正であるとみなされる。個人の財産を、政府が恣意的かつ強制的に取り上げる権利など、存在しないというわけだ。
再分配政策に否定的なリバタリアニズムと対照的なのが、現代的リベラリズムである。現代的リベラリズムの実質的な創始者は、ハーバード大学の哲学科でノージックと同僚だったジョン・ロールズである。
ロールズは、誰にでも普遍的に保障された権利として、「正義の二原理」というものを説いた。このうち第一原理では、「基本的諸自由の平等」が主張される。基本的諸自由には、政治、言論、思想の自由や、生命や財産に対する所有権の保障が含まれる。この第一原理に関しては、リバタリアニズムとほとんど変わりがない。
それに対して第二原理では、「できる限りの社会的・経済的な平等」が要求される。これには当然再分配政策も含まれるので、この点がリバタリアニズムと対立するわけである。
政治哲学にはここで紹介したリバタリアニズム、リベラリズムといった立場以外にも、コミュニタリアニズムなどさまざまな立場がある。本書ではそれらの立場が丁寧に腑分けされ、適切な解説が施されている。現代正義論には、どのような考え方があるのか知りたいと思った際に、本書は格好のガイドとなるであろう。
「失われた30年」とも言われる長期の不況に喘ぐ日本。このような状況になってしまった原因にはさまざまなものがあるが、中でも深刻なものとして、世間に間違った経済の知識がはびこってしまっていることがあるだろう。本書は、内閣官房参与の浜田宏一と日銀審議委員の安達誠司が、そうした俗流の間違った経済の知識を正すために執筆したものである。
本書でまず間違った経済論の筆頭に挙げられているのが、日本総合研究所の藻谷浩介による、「人口減少デフレ説」である。デフレでは経済の状況はよくならない。それならば、日本経済の長期停滞の主因をデフレに求めるのは正しいように思えるが、人口減少デフレ説の一体何が問題なのだろうか。
藻谷らの主張はこうである。日本経済の長期停滞の原因はデフレにある。そして、日本のデフレは、少子高齢化による生産年齢人口の減少によって引き起こされていると考えるのである。
生産年齢人口とは、15~65歳未満の現役世代の人口のことである。生産年齢人口の減少とは、すなわち、現役世代の人口が減っているということを意味している。日本人の人口の中で現役世代が減少すれば、消費活動は低調となる。それゆえ、物が売れなくなった企業は価格を下げざるを得ず、物価の下落が生じるというのだ。
浜田は、こうした藻谷の主張はまったくの間違いであると指摘する。それは、きちんとデータを確認してみればよく分かる。生産年齢人口の増加率を確認してみると、日本は-0.9%である(2007年~2012年平均)。それに対し、日本よりも生産年齢人口の増加率が低いのは、ラトビア(-2.6%)、リトアニア(-2.3%)、ブルガリア(-1.4%)の三か国である。
それでは、藻谷の主張するように、これらの国は日本よりもひどいデフレに陥っているのであろうか? 再度、データから確認してみよう。日本のインフレ率は-0.2%(2007年~2012年平均)。対してラトビアは4.9%、リトアニア(4.8%)、ブルガリア(4.9%)となっている。なんと、日本以外のどの国も、デフレになどなっていないのだ。
もし、藻谷の主張するように、人口減少がデフレの原因であるのなら、これらの三か国もデフレになっていなければおかしい。だが、現実はどの国もインフレなのだ。ここから分かることは、人口減少とデフレの間には、何の因果関係も無いということである。
人口減少デフレ説のような、何の根拠もない話でも、誰も顧みるものがいないのなら安心だ。しかしながら、藻谷の著書はベストセラーとなっており、その主張は世間の多くの人々に受け入れられている。そのうえ、さらに問題なことに、日銀の白川方明前総裁までが、藻谷の考えの支持者だった。これでは、日本人の間に間違った経済知識がはびこってもおかしくない。
デフレを脱却するのに必要な経済政策は、人口増加ではない。世界的に標準のマクロ経済政策は、金融政策と財政政策である。不況時には特に需要が不足してしまうため、財政政策として減税と公共投資を行うのが経済政策の王道である。
だが、そうした財政政策も、適切な金融政策無しには十分な効果を発揮しない。財政政策のみで金融政策が伴わなければ、過度な円高を招いてしまい、輸出産業に大きなダメージを与えてしまうのだ。
本書を読めば、このように何が正しく、何が間違った経済政策なのかが分かるようになる。社会人に必須の教養を身に着けるためにも、ぜひおすすめの一冊だ。
1991年のソビエト連邦の崩壊以降、左派思想の凋落が激しい。また、近年では中国が権威主義体制を強め、周辺諸国の警戒が高まっている。
そうした左派思想の退潮とは対照的に、近年注目を集めている思想が保守主義である。最近人気のYouTubeでも、保守を標榜したチャンネルは人気である。
だが、その一方で、「保守主義とは何か?」と尋ねられたら、明確に答えられる人は少ないのではないだろうか? 本書は、そうした素朴な問いに明確な答えを与えられるものとなっている。
本書の著者である宇野は、保守主義とは、社会主義のように一貫した理論的体系を備えた思想ではないと指摘する。保守主義とは、自らの強固なドグマを構築するものというよりはむしろ、フランス革命や社会主義といったその時代ごとの過激思想に対抗するための思想だというのである。
そうした対抗思想としての保守主義を、歴史上最初に提唱したのは、18世紀のイギリスの思想家、エドマンド・バークである。バークはその生涯を通じて、常に弱者の味方であった。アメリカ独立戦争の折には植民地側の立場を擁護し、インドでは東インド会社の不正を糾弾するなど、社会正義の追及がバークの一生のテーマだったのである。
そのため、フランス革命がおこったとき、多くの人々はバークが革命を支持すると考えた。ところが、そうした人々の予想に反して、バークは革命に反対の立場をとった。それはなぜか?
フランス革命は、度重なる増税に対して、人々の怒りが爆発したところから始まった。しかし、やがて革命運動が盛り上がると、革命の指導者たちは急進的かつ観念的になり、独裁政治を生み出した。革命運動の結果として、ロベスピエールによる恐怖政治が生み出されたのである。フランス革命による最終的な犠牲者は、200万人以上にも上ると言われている。
バークはその著書である『フランス革命の省察』の中で、こうした革命の急進性や独善性を批判した。いくら自由や平等という理念を追求するためであっても、その権力が専制化してはならない。また、伝統というものは長年にわたる叡智の蓄積でもあるのだから、それを急激に破壊してしまうことは、危険を伴う行為なのである。
こうした保守主義の真髄を、宇野はコンパクトに定義している。保守主義とは、「①具体的な制度や慣習を保守し、②そのような制度や慣習が歴史のなかで培われたものであることを重視するものであり、さらに、③自由を維持することを大切にし、④民主化を前提にしつつ、秩序ある漸進的改革を目指す」ものなのである。
保守主義の敵は、フランス革命だけではない。上記の定義に従うなら、社会主義もまた、保守主義の敵である。フランス革命を徹底的に批判したバークと並び、社会主義に対する最も鋭い批判者は、経済学者のフリードリヒ・ハイエクであった。ハイエク自身は、自らを保守主義者と名乗ることはなかった。だが、自生的秩序を重んじ、一党独裁の共産党が全能の指導者のように振る舞うことは傲慢であり、思い上がりであると批判を続けたハイエクは、自らが意識せずして保守主義の最も優れた美質を備えた思想家であったと言えるだろう。
ハイエクのように、自ら保守主義者を名乗らずとも、その思想の中に保守主義のエッセンスを含んだ思想家は数多い。本書の中で宇野は、そうした思想家の一人としてリバタリアンとして知られるロバート・ノージックの名を挙げている。ノージックもまた、ハイエクと並んで社会主義を嫌悪し続けた思想家だ。
これだけ多様な角度から「保守」を取り上げながら、本書の記述は極めて平易である。保守主義の入門書として、確実におすすめのできる一冊である。
経済学に関心のある方で、ポール・クルーグマンの名前を知らない人は少ないだろう。ノーベル経済学賞受賞者にして、ベストセラーとなった経済学教科書の著者でもあるクルーグマンは、長年ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニストも務め、アメリカ政府の経済政策にも大きな影響を与える存在である。
本書は翻訳者の大野和基によるクルーグマンへのロングインタビューをまとめたものであり、日本語オリジナルの企画である。クルーグマンの著書はたくさんあるが、その中でも本書は口述のため読みやすく、日本政府の経済政策に対する言及も多いため、初めてクルーグマンの本を読む読者におすすめできる一冊と言える。
アベノミクスが発表されたとき、日本では多くの識者がこのような政策は成功しないと、否定的な意見を述べた。クルーグマンは、こうした考えはナンセンスであると一蹴する。アベノミクスとは、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」から成る政策パッケージである。経済学の教科書を紐解いてみれば、どの教科書にも間違いなくマクロ経済政策とは、金融政策と財政政策の二つから成り立っていることが書いてある。つまり、アベノミクスとは経済学的にみて、当たり前の経済政策を主張しているものなのだ。
それではなぜ、私たちはアベノミクスによって、経済がよくなったと実感できないのだろうか? その原因は、2014年と2019年の二度にわたる消費税の引き上げにある。本来、不況期にあっては、財政政策として減税をおこなうというのが、経済政策の常道である。減税をすべき時期に増税してしまったのだから、景気が改善しないのは当然のことである。
本書が刊行されたのは、消費税増税の前の2013年である。当時、IMFやOECDはしきりに日本に対し消費税を増税するよう勧告していた。クルーグマンは本書の中でそれらの提言はまったくの間違いであり、日本はこのような勧告にしたがってはならないと警告していた。だが、結果としてクルーグマンのアドバイスは活かされず、アベノミクスは当初想定していたほどの効果を上げることができなかった。
しかしながら、なぜ減税をするのが当然な局面で、IMFやOECDといった国際機関は日本に増税を勧告したのだろうか。実のところ、IMFが当時緊縮政策を推進していたのは、日本だけではなかった。2010年以降、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルといったEU各国で緊縮政策は実行され、各国の経済は徹底的に破壊されてしまった。
こうしたIMFの緊縮政策の理論的根拠となったのが、ハーバード大学教授のカーメン・ラインハートとケネス・ロゴフの論文である。ロゴフらは「政府債務のGDP比率が90%を超えると、その国の経済成長が大きく停滞する」とその論文で主張した。彼らの論文を後ろ盾としてIMFはEUで緊縮政策を実行したが、のちになって何とこれはエクセルのマクロの間違いによる集計ミスであることが発覚した。彼らの説には、何の根拠もなかったのである。
そうした事実があるにも関わらず、日本では消費税5%から10%への大増税が安倍政権で実施されてしまった。だが、もはや緊縮政策にはいかなる理論的根拠もないことが、ロゴフらの論文の間違いから分かっている。間違った経済政策を改めるのに、遅すぎるということはない。一日も早く緊縮政策を改め、消費税減税へと舵を切ることが大切だ。
そして、財政政策を正しく実行することと同じくらい大事なのが、金融政策だ。本書の中でクルーグマンが主張するように、金融政策と財政政策の双方が正しく実行されてこそ、日本の不況からの脱出は可能となるのである。
アメリカでジョン・ボルトン前大統領補佐官が回顧録を出版し、大きな話題となっている。この回顧録の中でボルトンは、トランプ大統領が日本に対し、在日アメリカ軍の駐留経費の日本側の負担を現在の約4倍にあたる80億ドルに増額することを要求したと暴露した。日本政府はこれまで、このような要求があったことを否定する声明を出してきたが、ボルトンの告白は、実際にそのような要求が存在したことを裏付けるものとなった。
もともとトランプ大統領は大統領選挙運動の段階から、自分が大統領になったら、駐留米軍経費の大幅な増額を日本に要求することを明言していた。そして、その勧告に日本が従わなかった場合、米軍を撤退させることまで示唆したのである。
本当に、在日米軍が撤退してしまうことなど、あり得るのだろうか? 本書の著者の小川は、そのようなことは絶対にあり得ないと明言する。トランプ大統領は選挙公約ということもあり、そのような要求をする可能性はあるかもしれないが、日米間の軍事常識に照らし合わせて、在日米軍の撤退などということは実現不可能だというのである。
このような小川の主張は本当だろうか? アメリカの実際の行動と照らし合わせてみると、その正否がよく分かる。2017年2月、トランプ政権の閣僚として初めて、ジェームズ・マティス長官が来日した。安倍首相や稲田防衛大臣と会談したマティス長官だが、彼は決してトランプ大統領が主張するような、駐留米軍経費の大幅な増額を日本に要求することはなかった。そして、会談後の記者会見では、日本の駐留米軍経費負担は他国が見習うべき手本だとまで述べた。
こうしたマティス長官の発言は、決して個人的意見やリップサービスの類ではないことが、データを見るとよく分かる。アメリカの同盟国の経費負担割合を確認してみると、日本が負担率はトップで74%となる(2002年度)。そして、それに対して負担率2位のイタリアでも41%、韓国が40%と続く。イギリスなどに至っては27%しか負担していないのである。
このような現実を前にして、日本に更なる駐留米軍の経費負担を求めるのは、さすがに無理があるだろう。日本に更なる経費負担を求めることは不可能であると判断したアメリカは、他の同盟国に対し負担を求めていくように戦略を変更した。日本に来日後、NATOの国防長官会議に参加したマティス長官は、NATO加盟国にGDPの2%を目標値とする防衛費の増額を求めた。この基準を超えているNATO加盟国はわずか4ヵ国のみであり、この現実を踏まえると、日本にさらなる駐留米軍経費の負担を求めることが難しいことがよくわかる。
データをきちんと確認してみれば、アメリカの同盟国の中で、日本が最重要の軍事的パートナーであることは明白だ。日本が負担しているのは、駐留米軍の経費だけではない。アメリカは、日本にトータルで1107万バーレルの燃料を軍事用に貯蔵している。かつてアメリカがフィリピンに持っていた軍事拠点である、スービック海軍基地の燃料貯蔵能力が240万バーレルであることを考えると、これがいかに大きな数字であるかが分かるだろう。
日本がアメリカに提供しているのは、燃料貯蔵基地だけではない。普段あまり意識されていないことだが、アメリカの原子力空母ロナルド・レーガンの母港は、日本の横須賀である。アメリカの空母で海外を母港としているものは、これ以外無い。ロナルド・レーガンは日本を拠点としているからこそ、中国に対する抑止力として機能するのである。
日本がアメリカの国防に寄与している点は、非常に大きい。まずは、この現実を正しく理解することが大切である。日米同盟における日本の重要性を理解してこそ、アメリカに対して日米地位協定の改善を要請することも可能となってくるのではないだろうか。
「歴史を学ぶ」といったとき、私たちはどんなことを想像するだろうか? 多くの人にとってそれは、大学受験のための日本史や世界史の勉強のことであったり、歴史小説などを通じて、過去の英雄たちの姿に触れることであったりするかもしれない。
本書の著者である與那覇潤は、そうした形で私たちが触れる、通俗化された歴史の知識は、最先端の歴史学の知見からは程遠いものであることを指摘する。そして、本書を読めばそうした古い知識を最新のものにアップデートすることが可能であると断言する。
一例を挙げてみよう。日本における武士の時代の始まりについてである。通俗的な理解では、一旦は絶大な権力を手に入れたものの、驕り高ぶり、貴族化してしまった平家を侍の魂を持った源氏が打ち滅ぼし、武士の時代を到来させたと考えられている。
こうした考えは、まったくの間違いであるというのが、與那覇の意見である。平安時代、日本は農業と物々交換を主とした経済だった。そこで後白河法皇と平清盛は、対中貿易によって宋銭を日本に流入させ、日本に貨幣経済を確立しようとしたのであった。宋銭の存在によって利便性は高まり、経済は発展していく。平家の栄華は、こうした宋銭の輸入によって成り立っていたのである。
だが、こうした革新勢力には、抵抗勢力がつきものである。宋銭の導入によって、経済のグローバリゼーション化を推し進める平家は、従来の荘園経営によって財を成していた貴族や、経済的な繁栄に乏しい関東圏の武士(源氏)たちの目の敵となる。そして、打倒平氏の旗印のもと団結した彼らによって、平家は滅ぼされてしまうのである。
高校レベルの日本史の知識ならば、平家を滅ぼした源氏が、鎌倉時代という新しい世を作ったと考えても無理はない。だが、実際の歴史はまったく逆であった。貨幣経済を基として、日本を豊かな国、新しい国に作り変えようとしていたのはあくまで平氏であって、その平氏の邪魔をし、滅ぼしてしまった抵抗勢力こそが源氏だったのである。
日本社会をこのように「グローバル化派」と「反グローバル化派」に分け、両者の熾烈な争いこそが、日本の歴史を形作ってきたと考えるのが與那覇史観である。そして、與那覇は世界志向という意味で、グローバル化を「中国化」という異名でも呼んでいる。本書のタイトルである『中国化する日本』はそうした意味であって、決して日本が中国の属国になってしまうとか、日本文化が中国化してしまうといったものではない。
中国化派と反中国化派の戦いは、源平合戦以降も続いていく。平家の次に日本を中国化させようとしたのは、後醍醐天皇である。後醍醐天皇は宋朝の皇帝専制を日本に導入しようとするが、平氏が源氏に阻まれたのと同様に、反中国化派の代表である足利尊氏によって吉野へと追放されてしまう。源平合戦に続き、日本をグローバル化させようとする勢力は、またしても敗れ去ってしまったのである。
その後も散発的に日本を中国化しようとする試みはあるものの、ほとんどの場合、それは潰えてしまった。そして、日本は反中国化の極みともいえる、独自の江戸時代へと突入していくのだ。
このように日本史を中国化派と反中国化派の戦いの歴史と読み解く與那覇の解釈は、極めてユニークなものである。だが、それは決して彼の独創ということではなく、最新の歴史学の研究成果に裏打ちされたものであるということは、本書に付された出典を見ればわかるだろう。中国が存在感を増している昨今、こうした形で日本と中国の歴史を見直してみることは、たいへん有意義なことと思われる。記述は極めて平易で、歴史学の初心者にもおすすめできる一冊だ。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の拡大が、世界で問題になっている。これまでにも、新型インフルエンザやSARSといった感染症が世間を騒がせてきたことはあったが、今回のCOVID-19はその感染力も強く、世界経済が深刻なダメージを受けるほどの事態となっている。
このような事態を受け、世間では感染症に対する関心がこれまでになく高まっている。本書の著者の山本は感染症の専門家。アフリカ、ハイチなどで感染症対策に従事した経験もある上、歴史にも造詣が深いため、人類と感染症の歴史を解説するのにうってつけの人物だ。
狩猟採集時代の人類は、いたって健康であった。運動量が多いため、現代人のように生活習慣病にかかることもなく、化学物質もほとんど存在しないため、がんなどになることも少なかった。また、頻繁に移動するため、重病人は置き去りにしていたことも、共同体内に感染症が蔓延することを防いでいたという。
人類にとって感染症が脅威となったのは、移動社会(狩猟採集社会)から、定住社会となったためである。農耕の開始によって、飛躍的に人口が増大した定住社会では、共同体の規模も大きくなっていった。メソポタミア、中国、インド亜大陸といった古代文明発祥の地において、人類の間に初めて麻疹や天然痘、百日咳といった感染症が定着していったのである。
山本の分析の興味深い点は、これらの感染症が、人類にとって必ずしもネガティブな意味だけをもっていたのではないと指摘するところにある。感染症に恒常的に見舞われる社会は、それによって人口の何割かを失うが、集団が免疫を獲得する。そうして獲得された集団免疫が、免疫を持たない外部の異民族から攻撃された際に、ある種のバリアーの役割を果たすというのである。私たちは感染症というと、即悪いものであると考えてしまいがちだが、社会にとっては有用なケースもあり得るという指摘は興味深い。
歴史上、同じようなケースは他にもあった。ペストは元々中国に起源を持つ病気だが、モンゴル帝国がユーラシア大陸を統一した頃、その交通網を介してヨーロッパ全土に広まり、ヨーロッパ全人口の三分の一近くの人々が亡くなったと言われている。
これほど大量の人口が一気に失われれば、当然社会、経済的な構造も変化を余儀なくされる。極端な人手不足に陥ったため、労働者の賃金が急上昇したのである。その結果、経済的な余裕を持った市民も生まれ、その中から新しい思想や文化が生まれていった。旧体制の象徴だった教会の権威は相対的に低下し、そこからやがてイタリアを中心としたルネサンスがヨーロッパ社会に広まっていったのである。
感染症は文化だけでなく、科学の発展にも大きな影響を与えた。1665年から66年にかけて、イギリスでペストが大流行した。ロンドンの死者は10万人を越え、COVID-19が流行している現代と同様に、大学は閉鎖された。その頃、閉鎖されたケンブリッジ大学に通っていたのがアイザック・ニュートンである。ペストから逃れ故郷に疎開していたニュートンは、18ヶ月間の自由になった時間を活用し、微分積分や万有引力の法則といった歴史に残る業績を挙げたのである。
本書の末尾で山本は感染症の根絶は現実的ではなく、むしろ感染症と人類の共生といった発想が必要であると説く。現代でも、ウィズコロナという言葉で、COVID-19との共存・共生がしばしば語られる。COVID-19の感染拡大によって暗くなりがちな昨今ではあるが、かつてのペスト禍にあっても逞しく生きたニュートンたちに学びつつ、前向きに生きていきたいものである。
2020年5月、アメリカのミネアポリスで黒人男性のジョージ・フロイドが、白人警官に約9分間にもわたり頸部を圧迫し続けられ、窒息死させられるという事件が起こった。アメリカではこれまでにも白人警官による黒人への理由なき暴力が多発しており、これに抗議したBlack Lives Matter(「黒人の命も大切」という意味)の運動が、現在全米で大きな盛り上がりをみせている。
リンカーンによる奴隷解放宣言は、1862年のことである。それから160年近く経とうとする現在、なぜ今もなお黒人への差別は残っているのだろうか。本書は、そうしたアメリカにおける有色人種や少数民族への差別の背景を、詳細に解説したものである。
皮肉なことに、黒人に対する排外運動は、リンカーンによる奴隷解放宣言の直後に最初の大きな盛り上がりをみせた。排外主義団体である、KKK(クー・クラックス・クラン)の結成がその嚆矢である。KKKは、南北戦争で敗れた旧南部連合の有力者を中心に、テネシー州で結成された。初期のKKKは解放された黒人奴隷や、彼らを擁護する白人を攻撃の対象としていたが、その隆盛は長くは続かなかった。
KKKが下火になったのは、アメリカ人が差別を悔いたからだろうか? 残念ながら、そうではなかった。ジム・クロウ法と総称される、白人と黒人を人種隔離する法律が施行されたことが、KKKの活動が退潮した理由である。ジム・クロウ法には、電車やバスなどの公共交通機関やレストランなどにおいて、白人と黒人を隔離することが含まれていた。言うなれば、差別が制度化されることによって、より過激なKKKの活動が終息していったのである。
こうして一旦は社会から消え去ったKKKだが、40年ほど後に意外な形で復活を遂げる。きっかけは、D・W・グリフィス監督による一本の映画だった。『国民の創生』と名付けられたその映画は、KKKを悪の黒人を懲らしめるヒーローとして描いた。そして、映画に影響を受けた多くの人々がKKKの活動にのめり込んでいくこととなる。
荒唐無稽なKKKの世界観に心酔したのは、粗野で無学な人たちばかりではない。日米戦争当時の大統領だったハリー・トルーマンや、連邦最高裁判事といった名士にも、KKKのメンバーは多くいた。
アメリカに蔓延する差別主義は、日本人にも影響を与えた。1920年代になると排日移民法が施行されたが、この法律の制定に大きな影響を与えた法律家であるマディソン・グラントは優生学者であり、その著書はアドルフ・ヒトラーによって絶賛されている。当時のアメリカにはそれほど、レイシズムが根付いていたのである。
このようにアメリカの歴史そのものが差別の歴史であると言っても過言ではないほど、差別の根は深い。なぜ、これほど人は差別に心惹かれるのだろうか? 本書の著者である渡辺は、その原因を陰謀論的世界観にみる。
一般に黒人差別の団体とみなされがちなKKKだが、実際には攻撃の対象は黒人だけでなくユダヤ人も含まれる。ユダヤ人が世界の金融市場やアメリカ政府を牛耳っており、影から操っているというのが彼らの主張である。
こうした陰謀論的世界観は、決して対岸の火事ではない。TwitterやFacebookといったSNSを見てみれば、さまざまな形の陰謀論が巷にあふれていることがわかるだろう。そして、その典型的なものは、特定の民族や集団が世界を牛耳っているというものであり、それらに対する被害者意識から、憎悪をぶつけているものが数多くみられる。
そうした陰謀論に惑わされないようにするためにも、アメリカの差別の歴史を知ることは有益だ。本書はそのようなアメリカの闇の歴史を知るための、格好の入門書と言えるだろう。